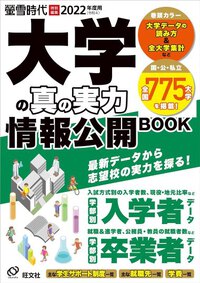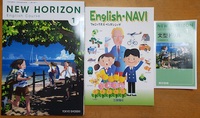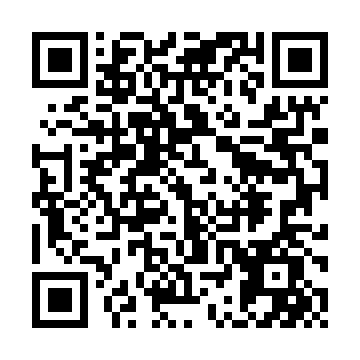2014年02月28日
グローバル企業・Google

こんにちは。
一昨年(2012)の夏、Google 東京オフィスを訪問したこともあり、Googleへの興味と畏怖の念はつきません。
本日(2014年2月28日)、Google のブラウザー(閲覧ソフト)である Chrome の日本における開発リーダーの及川さんの記事が日本経済新聞のWeb刊に出ていました。
中学生・高校生が進路を考える上でとても参考になると思いますので、長いですが例によって(汗)全文引用してみたいと思います。
--------------------------------
「25分の掟」 グーグルが会議でつむぐ価値 (及川卓也)
「どうすれば日本でもグーグルのような企業が生まれるだろうか」と聞かれることがよくあります。まず、個人の能力という面では日本人は世界のどの地域に行っても引けをとらないと思います。ソフトウエア開発に携わる日本人エンジニアの能力は非常に高い。例えば日本で活躍するトップクリエーターが米国シリコンバレーでベンチャー企業を興したら、現地の有力企業と互角に戦えるでしょう。
お付き合いのある電機業界や通信業界、自動車業界などの大手企業で働くエンジニアの顔ぶれを思い浮かべても、みなさん本当に優秀です。
■組織の中でイノベーションの芽をつぶしていないか
日本でも、高い能力を備えるエンジニアを支える環境が用意されれば、企業がより活性化しベンチャー企業も増えるだろうと思っています。前例のないサービスのような新しい芽を温かく見守り育てるカルチャーがあれば、世界で通用する企業が育つでしょう。
日本では現在の法律の観点でグレーとされると、産業界全体で守りに入ってしまう。たとえグレーでも利便性が高くて消費者の役に立つサービスなら、実現させられないかみんなで考える環境がイノベーションを生みます。
現状の枠組みでできないなら、どうすればできるのか――。シリコンバレーではまずこんな議論から始まります。ベンチャー企業が開発したからといって、軽んじられることはありません。本当に革新的なものであれば、その挑戦を称える風土がそこにあります。もちろん反社会的なものは誰も認めませんが、そうでないならできるだけ前向きに検討しようとします。
企業によっては法務部門の厚い壁にぶちあたってサービスを始められないケースもあります。グーグルではその内容によって、当然法務部が徹底的にリスクを分析します。彼らは役割として安全サイドから主張をするのが当たり前ですが、法務部が「ダメだ」と意思決定はしません。リスクをすべて提示したうえで、最終的な意思決定は現場や経営陣に任せるのです。
イノベーションよりも失敗を恐れているとすれば大変残念です。意思決定する際に安全サイドばかり重んじていたら、本来生まれるべき斬新なサービスはまず生まれません。エンジニアたちが萎縮し、持て余している能力を組織の中ででつぶしてしまうのは本当にもったいない。
組織によっては一度失敗すると、その評価が定着してしまうと耳にしたことがあります。グーグルでは、成功もしない代わりに失敗もしないような変化を求めない人間は無能とみなされます。失敗して学ぶほうが何もしないよりも尊ばれるのです。
■技術が分かる上司が評価しなければ部下は伸びない
グーグルではエンジニアの実力を最大限引き出せるよう、社内の人事制度に気を配っています。評価制度もその一つです。たとえば上司が部下であるエンジニアを適正に評価するためには、エンジニア1人ひとりの業務をきちんと理解していなければなりません。人事評価として360度評価システムを採用しているのですが、それでも最終的には上司が評価を取りまとめます。
もし上司が技術が分からない人間だったら、エンジニアはそんな上司に評価されることを不満に思うでしょう。グーグルではエンジニアリング部署で働く社員は、すべてエンジニアリングのバックグラウンドがあります。直属の上司だけでなくその上司、さらにその上司に至るまで、コンピューターサイエンスの素養があるか同等の業務経験がある人間ばかりなのです。
一般的な日本企業では人事異動でさまざまな部門を経験させて、ゼネラリスト(総合力がある人材)を育てることが多いと聞きます。グーグルの場合、ゼネラリストを育てるための人事異動はありません。つまり自分の部署に突然、技術を全く知らない担当者が異動してくることはないのです。
エンジニアリング部門で採用した社員は、その部門の中で昇進していきます。企業によっては一定以上の職位につくには管理職にならざるを得ない場合もあるようですが、必ずしも管理職になる必要はありません。管理職として働く「エンジニアリング・マネージャー」になるかは本人が決められ、管理職でなくても成果を出せば同様に評価されます。管理職が偉いわけではなく、管理職も管理職でない社員もそれぞれの役割に応じ技術的な成果が期待されます。実際、管理職ではないが職位の高い社員は山ほどいます。
いずれにしろ、エンジニアは純粋に技術的な貢献において正当に評価されるのがグーグル流。エンジニアリングで成長した会社だからこそエンジニアを大事にするカルチャーが根づいている。それこそがグーグルの強さの根源といっていいかもしれません。
もう一つカルチャーの話をすると、グーグルでは社内ミーティングを開催する際に、本当に必要なのかが問われます。単なる情報共有ならばメールでできます。ミーティングは議論するためのものですから、通常のミーティングでは8人程度の出席者が最大です。
またミーティング時間は25分が基本です。定刻で終わらせるため、全員が全力投球するのが掟(おきて)です。24時間前までに議題が送られ、事前に資料などは目を通していることを理想とします。資料はすべてオンラインで用意されますので、ミーティングで配布物があることはまれです。
議題と資料は事前にメンバーに提示されているので議論はすぐにトップスピードで交わされ始めます。そして終了時間5分前ごろに、実行しなければならない事項を整理してクロージング(まとめ)に入ります。まとめた結果はミーティング終了後速やかにメールなどで出席者同士で共有します。スピードがグーグルの命ですが、ミーティング一つとっても素早いテンポで進めることに強いこだわりがあります。
■「メード・イン・ジャパン」の本当の価値
日本のモノ作りについてときどき感じるのが、「メード・イン・ジャパン」という単語による呪縛です。日本という国や言語の特殊性をあまりにも前面に押し出すモノ作りは、少々時代錯誤に思います。海外の製品・サービスが当たり前に国境を超える今、ダイバーシティー(多様性)を前提にしたモノ作りが大切なのではないでしょうか。
例えばグーグルの社員なら、おそらく誰一人として米国企業で米国産のネットサービスを開発しているという感覚を持ち合わせていないはずです。開発に携わるウェブブラウザーのクロームが米国産のソフトかといわれれば、個人的には大きな違和感を覚えます。たまたま本社が米国にあるだけで、グローバル企業の一員として政府や国境の枠を超えて世界で普遍的に受け入れられるものを作りたい。みんなそう思って働いています。
もちろんローカライズの考え方は必要です。例えば地図サービス「グーグルマップ」では、近くのお店を検索する対象エリアの範囲をその地域の特徴に合わせて変えています。米国では車での移動を前提に検索結果を表示しますが、日本の場合は徒歩圏内を想定して検索結果を表示しています。日本にそのまま持ってきても使い勝手がよくないからです。
ローカライズしつつユーザー体験が国境を超えて受け入れられることを目指しながら、ダイバーシティーに沿った揺るぎない「ワンプロダクト」を生み出す。この点でグーグルはぶれません。
ではシリコンバレーへ渡らずに、日本に住みながらダイバーシティを踏まえたモノ作りができるかと問われれば「当然できる」と断言できます。まだまだ日本には世界に誇れる先進的な技術がたくさんあり、少子高齢化という他国がこれから経験するであろう社会的な問題も抱えています。この国に住んでいるからこそ知ることができ、開発に生かせる種がこの国にはあるのです。メード・イン・ジャパンの本当の価値は、日本から世界を見て初めて理解できるダイバーシティーのあるモノ作りにあるのだと私は信じています。
--------------------------------