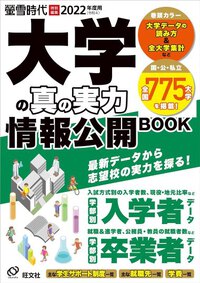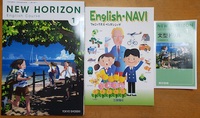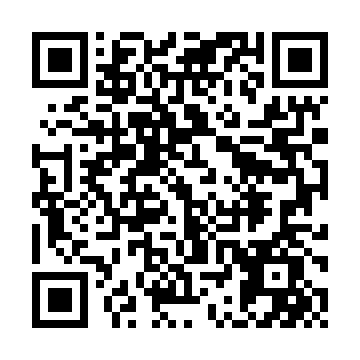2014年04月06日
『学ぶ』ということ

こんにちは。
2014年春、大阪大学大学院教授・仲野徹先生が大学院生向けに行った入学ガイダンスでの挨拶がとても素晴らしいので、全文引用させていただきます。
--------------------------------
平成26年度 大阪大学大学院生命機能研究科 入学ガイダンス 挨拶
『学ぶ』ということ
桜が咲き誇り、お天気にも恵まれ、キャンパスが一年中でいちばん美しい日に、新しい仲間を迎えることを、本当にうれしく思います。
今日は、『学ぶ』ということについて、少しお話したいと思います。ライフネット生命保険・会長の出口治明さんという方がおられます。稀代の読書家でもあられる出口さんは、人間が学ぶ方法は三つある、とおっしゃっています。一つは本、活字から学ぶこと、二つ目は、旅、自分の脚で歩いて世界から学ぶこと、そして、人、人間に会って話を聞いて学ぶこと、です。
まず、本から学ぶ、ということです。いちばん効率がいいのはこれかもしれません。じっとしているだけで、過去の賢人たちと対話ができるのです。それも自分のペースで。いまは、ネットの情報も、本に学ぶという範疇にいれてもいいかもしれません。
旅で学ぶ、あるいは、じぶんの足で学ぶ、というのも大事なことです。本やネットというのは、うまくまとめられてはいますが、やはりバーチャルです。それに、他人の目を通してものを見ることにすぎません。横着をせずに、手間と時間がかかっても、自分の目で確認する、ということが重要です。
人から学ぶ、というのは、本や旅から学ぶ、というよりも高度なことです。本や旅というのは、自分でやろうと思ったらできることです。しかし、人から学ぶのには、相手がいります。このことをおこなうには、自分自身を磨き上げること。学びたいと思う相手に、この人なら教えてあげたい、という気持ちを持たせることが大事です。
しかし、それだけの価値はあります。自分の考えというのは、慣れ親しんだものですが、どうしても、檻の中にはいったようになっていきます。それを打破するためには、人から学ぶ、ということが肝心です。
では、研究において「学ぶ」ためには、何が必要でしょう。これも、同じように考えたらいいのではないでしょうか。
まず、本に学ぶ。なにかを学び始めるには教科書を読むことが必要です。いい教科書を読んで、何がわかっているのかを学ぶこと。そして、研究をする上においてそれ以上に大事なことは、何がわかっていないか、を読み取ることです。どのような重要な問題が残されているのか、を知ることなしにいい研究をすることはできません。
本の次に重要なのは、論文です。しかし、他人の論文を信用しすぎること、そして、文献ばかり読んで頭でっかちになることは避けなければなりません。研究者、科学者というのは、どれだけものを知っているかが大事なのではありません。自分のデータに基づいて自分の頭で考えることこそが重要なのです。
次に、旅、です。研究と旅というのは直接的な関係はなさそうです。しかし、自分でおこなって自分の目で見る、ということに置き換えることができるでしょう。『仲野の第一法則』と呼んでいるものがあります。それは「研究はしなければ進まない」ということです。失敗することもあるので、残念ながら、「研究はすれば進む」というものではありません。しかし、やってみないと始まらないのです。
そうやって得たデータは、本や論文から得た情報とは全く違います。厳密な言い方をすると、本当に百パーセント信頼できるデータは、自分でおこなった実験のデータだけです。もちろん、いままで言われていたことと、そのデータが違ったような場合は大発見である
可能性もあるのです。
そして、人。これも非常に大事です。「孤高の研究者」などというのは、過去の遺物です。いまや、膨大な知識が蓄積され、専門化が非常に進んでいます。その中で、時代を読み何が重要かを知るには、多くの人とコミュニケーションをとりながら研究を進めることが必要です。
たくさんの、いろいろな分野からの入学生が集まってくれました。まず、同士として、できるだけたくさんの友人をつくってください。もう、これだけたくさんの人と一気に知り合いになれるチャンスはないかもしれません。それから、教員の先生たちには、遠慮なく質問したりしてください。生命機能研究科の先生たちは、みなさんフレンドリーですばらしい先生ばかりです。
そうしたことをおこなうためには、自分を高めることが大事です。あいつと話をすると、こちらも勉強になる、あるいは、この子には教え甲斐がある、と思われるようになるべく努力することが大事です。
生命機能研究科は、融合研究を大きな目的としています。これはたやすいことではありません。どうしても、自分の専門以外のことを学ぶのはおっくうになります。そういった時に、人と人とのつながり、適切な先生を見つけ出して教えを乞う、というのはきわめて重要になります。
最後に、座右の銘としている、山本義隆さんの、何のために勉強するのか、についての言葉を紹介したいと思います。
「専門のことであろうが、専門外のことであろうが、要するにものごとを自分の頭で考え、自分の言葉で自分の意見を表明できるようになるため。たったそれだけのことです。そのために勉強するのです。」
研究し、それを自分の頭で考え、自分のことばで表現して、他の人たちと意見を交換する。サイエンスという営みはこういうものだと考えています。簡単なように聞こえるかもしれませんが、実際にはそれほどたやすいことではありません。そういったことができるように、これからの日々を送ってもらえたらなによりと考えています。
--------------------------------
また、こちらの仲野徹先生によるエッセイも大学生・社会人は必読です。
なんのために学ぶのか その1
なんのために学ぶのか その2
なんのために学ぶのか その3
なんのために学ぶのか その4