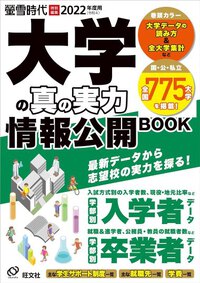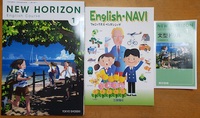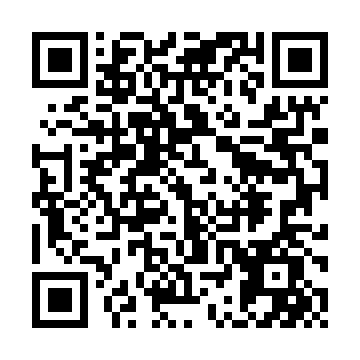2011年10月04日
常識からの脱却

こんにちは。
日曜日(2011/10/2)の日本経済新聞コラム「世界を語る」に上記『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』の著者である、クレイトン・クリステンセンさんが登場していましたのでメモしておきます。
凡人がスティーブ・ジョブズのような革命を起こすためには、以下の4つを習慣にすることが大切だとクリステンセンさんはおっしゃっているのですが、勉強ばかりの「高校生」にはぜひ勧めたいですね。(^_^;)
1.まず何に対してもなぜ、どうやって、といった疑問を持つこと。
2.周囲・外界を注意深く観察すること。
3.分野や文化の異なる人々と交流すること。
4.そして発見やアイデアを実際に試してみることだ。
---------------------------------
成長担う革新の方法とは
トップ先導で新事業を
ハーバード経営大学院教授 クレイトン・クリステンセン氏
世界を語る
日米欧が成長力不足に悩んでいる。日本は過去20年、成長を担う新しい企業・事業の不足という構造問題を抱えてきた。同期間にグーグルなどの新企業が次々大企業に育ち、アップルが新事業で時価総額世界一に上りつめた米国でも最近では雇用創出力に陰りが見える。成長のカギは既存の構造を打ち破る革新(イノベーション)だ。革新を促すヒントを米ハーバード経営大学院教授、クレイトン・クリステンセン氏に聞いた。
――近著「革新者のDNA」(邦訳未刊)で凡人でも革新を起こせると論じました。
「調査の結果、革新的企業のリーダーに共通するスキルが見つかった。最も大事なのは一見関係なさそうな事柄を結びつける思考だ。たとえばセールスフォース・ドットコムの創業者マーク・ベニオフはハワイの海で泳ぎながらアマゾン・ドット・コムの買い物サイトと勤務先だったオラクルの業務ソフトを同時に思い浮かべ、ネット上で業務ソフトを提供するというアイデアを思いついた」
「また、彼らは4つの習慣で『結びつけ』の材料を得ていることも判明した。まず何に対してもなぜ、どうやって、といった疑問を持つこと。周囲・外界を注意深く観察すること。分野や文化の異なる人々と交流すること。そして発見やアイデアを実際に試してみることだ。これらを実践すれば、スティーブ・ジョブズ(アップル会長)のような天才でなくても革新的なアイデアを得られる」
――現場に革新的なアイデアがあっても事業に生かせない企業が多くみられます。
「現場の革新と企業全体の革新には違いがある。成功している事業を担う組織の内部では、現場の革新的なアイデアは絶対に事業化されない。その組織の任務は既存の仕組みで収益を拡大することで、当面費用増加になる新規事業に投資するのは任務に反するからだ。そもそも革新的な新事業には既存事業と異なるコスト構造やビジネスモデルが必要だ。つまり新事業には既存事業とは別の組織が必要。それをつくって実行するのが企業レベルの革新だ」
「あるとき、典型的な成功企業である米スリーエムの研究部門が年商80億ドル規模の事業になりそうな画期的な新素材を開発した。ところが、予想粗利益率が55%以上でないと事業化しないという企業レベルのルールに従って事業化を見送った。従来の成功モデルとは異なるやり方を取り入れ企業レベルで大きく成長する革新の機を逃した。成功の方程式がかえって革新を妨げる『イノベーションのジレンマ』の典型例だ」
――大企業の多くが確立した成功モデルを持っています。大企業はジレンマを避けられないのでしょうか。
「例はある。IBMは高収益の大型汎用機で成功しながら、利益率の低いミニコンピューターやパソコンをそれぞれ別個の組織をつくって手掛けさせた。インテルはコモディティー化したメモリーを捨てプロセッサーに専念し高い利益率を実現した後、わざわざ廉価のプロセッサーに進出して他社による『破壊的革新』の芽をつぶした」
――破壊的革新にはどんな手段があるでしょうか。
「たとえば高利益率を目指すのが当たり前の業界で、あえて低利益率で勝負する。かつて米自動車産業は日本の自動車産業に高収益追求モデルを破壊された。品質が重要だったはずの米鉄鋼産業では、最低限の品質で低価格を実現した電炉が高炉をワキに追いやった。既存プレーヤーが利益の追求という当たり前の選択をすると、新参者による破壊的革新の余地を生みだす」
――成功企業がジレンマを回避するカギは。
「トップの役割が非常に重要だ。既存の成功事業とは違うビジネスモデルの新事業のために新組織をつくり経営資源を配分する判断はトップにしかできない。その後、既存部門の反発を抑えて新部門を後押しするのもトップの仕事だ。利益率と成長のどちらが大事かという判断もトップ次第だ。つまり企業レベルの革新はトップが革新的な発想を持てるかどうかにかかる」
「トップは往々にして収益の大部分を稼ぐ中核事業に注力しがちだが、実は中核事業は既に稼ぐ仕組みができあがっており放っておいても回るものだ。トップはむしろ将来の収入をどう稼ぐか考えることに集中すべきだ」
――利益率の追求は当たり前では。
「デルは台湾メーカーにまずパソコンの回路基板を、次にマザーボードを、最後に完成品の組み立て全体をアウトソースしていった。コストと資産が減り、純資産利益率が上がるからだ。台湾メーカーはデルに『組み立てはデルのコア競争力ではない』と提案し、デルもそう思った。だが気づくと全米の量販店に価格の安い台湾製の同等品が並んだ。デルは利益率を追求することで国内雇用を減らし、自らの競争力まで弱めた」
――自らのコア競争力を見誤っていたのが問題では。
「実は経営判断においてコア競争力は重要ではない。眼前に見えているコア競争力とは過去に成功をもたらした能力のことだからだ。経営者が注目すべきは変化する世界のなかで今後どんな能力が必要なのかという問題なのだ」

(画像をクリックすると大きくなります)
――日本は国全体が過去の成功モデルを脱却できていないようです。
「革新は決まって異なる分野や文化の交差点で起こる。シリコンバレーで成功した起業家の多くは外国人だ。シンガポールは外国の優秀な人材を積極的に流入させて革新力を増している。日本で革新が生まれにくい一因は、民族的純血主義にあると思う。もっとも同時テロ以降、米国も海外からの人材流入を難しくし、革新を生み出す能力を自ら損なっている。ハーバード大でもどこでも起こっていることで、非常に憂慮している」
「企業経営で危険なのが将来キャッシュフロー(現金収支)という物差しだ。ある事業が今後生み出す現金黒字を予想し、事業に必要な投資額を銀行預金や国債での利息収入と比べて、投資すべきか判断する。しかし何も新規投資しなければ企業は衰退する。つまり新規事業への投資と比較すべき対象は預金利息ではなく、衰退というマイナスの価値だ。経営大学院や株式市場で常識になっているこの投資家視点の物差しが企業にまん延すると革新が実行されにくくなり、国全体の成長力、雇用創出力を弱める。米国ではそれが起きていると思う」
Posted by 百武塾 at 20:15│Comments(0)
│レッスン日記