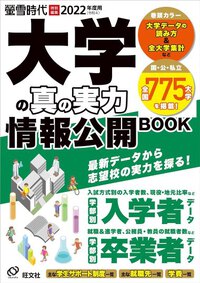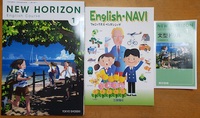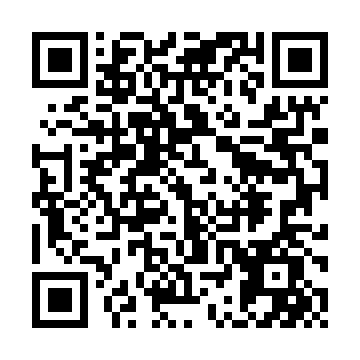2012年04月19日
英語で大学開国?

こんにちは。
昨日(2012/4/18)の日本経済新聞・朝刊の1面に「大学開国」というコラムの「第2部 世界で戦う条件」がスタートしました。
例によって(^_^;) 、ツッコミどころ満載なのですが・・・。
一番、笑ってしまったのは「教員の話を一方的に聞く従来型の講義では、グローバル社会で必要な『自分で考える力』は鍛えられない」のところで、
「『一方的に聞く』って、そもそも聞いてないんじゃない?」
「今までは国内だけだったら、自分で考えないの?」
「ということは、現状の大学教員は“ グローバル仕様 ” じゃないんだ!」
・・・・・
このあたりで止めておきますが(^_^;) 、大学だけの問題はなく、英語ができる・できないだけの問題でもありません。
アメリカの高校生はだいたい夜10時ぐらいには寝てしまう生徒がほとんどで、日本的な「受験勉強」はありません。
しかし、大学に入ると、勉強量は日米逆転します。上のグラフにあるように、確かにアメリカの大学生はよく勉強します。
アメリカの大きな大学では、図書館が24時間開放というのは普通です。
また、アメリカでは高校卒業後、家を出てアパートを借り、自分で仕事をしながら大学の授業料を払ったり、学資ローンで自ら借金をして学んでいる学生も普通にいます。
コラムにも「社会が大学教育に多くを期待しなかったことに甘え」とありますが、文系の学部では特にこの傾向が強いのではないでしょうか?
大学生のみなさん、グローバルに活躍できるよう、勉強しましょう!

---------------------------------
勉強しない学生 「白熱教室」で鍛え直す
第2部 世界で戦う条件(1)
2012/4/18付日本経済新聞 朝刊
東京大学の秋入学移行構想をきっかけに、大学の国際化やグローバル人材の育成に向けた議論が熱を帯びている。知の国際競争に打って出るためには何が必要なのか。日本の大学の課題を探る。
「5人を助けるために1人を犠牲にすることは正しいか」。教授の問いに学生が次々に手を挙げた。「個々の命の価値は同じ。5人の命の総和の方が重い」「犠牲になる1人が米大統領だったら話が違う」。17日、千葉大であった政治哲学の講義は「命の価値」を巡って約25人が発言。教室は熱気に包まれた。
同大は今年度、政治哲学の複数科目で教員と学生が意見を交わしながら進める「対話型講義」を本格導入する。手本は米ハーバード大の看板講義で、丁々発止の議論が学生の絶大な支持を集めるマイケル・サンデル教授の「正義」だ。
正解のない討論
学生は少人数ゼミで議論を重ねた上で、約150人が入る大教室での講義に参加。正解がない問題を巡る討論に挑む。「教員の話を一方的に聞く従来型の講義では、グローバル社会で必要な『自分で考える力』は鍛えられない」。小林正弥教授はその意義を強調する。
多くの大学がグローバル人材を育てるための教育改革に乗り出している。何とか学問に「白熱」してもらおうと躍起だが、肝心の学生はどうか。
産業能率大は4年前、経営学部で課題解決型の授業を中心に据えた。企業の商品企画などに参加する演習と、経営理論を教える座学を交互に受講。実践で知識不足に気付き、勉強するよう促す仕掛けだ。
「アクティブラーニング」として注目されるこの試みは卒業生の満足度も高い。ただ「アンケートに『授業以外では勉強しない』と答える学生もいる」(松尾尚教授)。受け身の姿勢を変えるのは簡単ではない。
大学全入時代となり学生の質は多様化した。大学が手取り足取り面倒をみなければグローバル時代に見合う人材は送り出せないのが実情だ。
偶数と奇数の和が奇数と証明できる大学生は3割――。日本数学会が昨年行った数学力調査は危機的な結果が並ぶ。「入試で記述式問題を出す大学が減り、高校も論理的に考えさせる訓練をしなくなった」と宮岡洋一理事長。中学・高校レベルの補習をする大学は今や珍しくない。
授業に手抜き
日本の学生の勉強時間は授業を含んでも1日平均4.6時間で、卒業単位取得に本来必要な8時間の約半分。調査した金子元久・筑波大教授(高等教育論)は「社会が大学教育に多くを期待しなかったことに甘え、授業に手間をかけてこなかった教員の責任は重い。そのうち留学生に見放され、日本人も送り出せなくなる」と警鐘を鳴らす。
教育の国際化には英語の授業をどう増やすかも課題だ。英語での授業を実施する日本の大学は2009年で全体の27%の194校にとどまる。ネックは教員の語学力だ。
母国語を大切にするといわれるフランス。パリの高等教育機関(グランゼコール)、HEC経営大学院は15年前から英語での授業を増やし外国から優秀な教員と留学生を集め、欧州トップのビジネススクールの地位を確立した。「英語重視に異論もあったが、グローバル化には不可欠と信じて決断した」(ベルナール・ラマナンスゥ学長)
「グローバル化が進み、国境という障壁が低くなっている。よりタフでよりグローバルな学生になってほしい」。秋入学構想を掲げる東大の浜田純一学長は12日の入学式で、新入生を激励した。
経済協力開発機構(OECD)は学生が大学で得た知識と技能を学問分野別に測るテストを各国で行うことを検討中。日本の大学教育の質が問われる時が来ようとしている。改革のために残された時間は少ない。
---------------------------------
Posted by 百武塾 at 21:15│Comments(0)
│レッスン日記