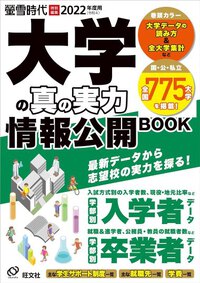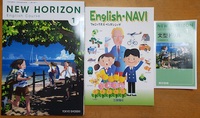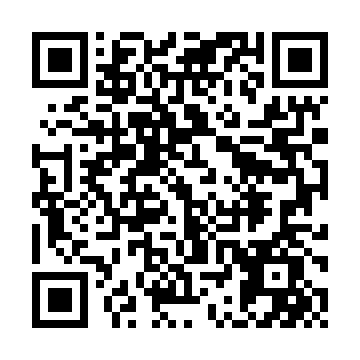2013年01月11日
国際思考のユニクロ

こんにちは。
昨日(2013年1月10)の日本経済新聞・朝刊の「辛言直言」というコラムに、いつも舌鋒鋭いファーストリテイリング(ユニクロ)会長兼社長の柳井さんが登場していました。
百武塾のブログでも
「ユニクロ社内英語」
「日本人学生は不要 増える留学生採用 ローソン、ヤマト運輸3割、ユニクロ6割」
と、何度かユニクロを取り上げています。
最近は
「ユニクロはブラック企業」
としてネットを賑わすこともありますが、「怒濤のグローバル経済」で世界一を目指そうとしているのであれば、しかたないことのような気もします。
柳井さんは2011年11月18日に「新卒一括採用を見直しへ 大学1年で採用も」と発表し大騒ぎになったのですが、実際に2012年6月8日には「大学1・2年生に内々定 ユニクロ、約10人に」と再び大騒ぎになりました。
私は
「大学1年生に内定を出すということは、大学教育を真っ向から全否定していることになるんだけど、特に文系の学部はその通りだものなあ~」
などとノンキに考えていたのですが、その理由を柳井さん自身が、今日のコラムで語っていらっしゃいます。
例によって(汗)長い引用ですが、是非、お読みいただければと思います。
---------------------------------
辛言直言
大学変えねば日本は沈む
1年生に内々定、その意味は
ファーストリテイリング会長兼社長 柳井正氏
ファーストリテイリングは傘下のユニクロで昨年の採用選考から大学1年生でも内々定を出す制度を始めた。大学教育の意義を否定するかのような行動に出た柳井正会長兼社長は大学に厳しい視線を送るだけでなく、学生にも注文を付ける。その底流には、大学のあり方を変えなければ「日本が沈んでしまう」という危機感がある。
――大学をどのように改革すべきだと考えますか。
「世の中がこれほど大きく変化していく中で、社会人になってから改めて勉強しようと考える人も多いはずだ。大学はいつでも勉強するために通えるような生涯学習の場に変わるべきだ。日本の大学は高校を卒業してそのまま入学する単線的な進路になっているが、もっといろいろなコースを用意したらいい」
「そのためには社会人の要求にこたえられる教員の技量も必要だ。大学教員は毎年、同じ内容の講義をしている。経済や経営などの社会科学は社会の動きとともに変化しているはずなのにアップデートしていない。どんどん社会から乖離(かいり)していっている。そんな教員は必要ない」
――大学の人事制度にも問題があるのでは。
「一度、教授になったら定年まで安泰な世界なんて変だ。ちゃんとパフォーマンスを発揮し続けないと、教授として大学には居続けられないような人事制度にしてもらいたい。変わろうとしない教授会が大学を牛耳っているから無理かもしれないが」
「大学教員は研究と教育の2つの役割があるが、教育をないがしろにしているような気がする。はっきり言うと教えるのが下手。教室で学生の前でなにかぼそぼそ話しているだけだ。学生もほとんど聞いていない。学生に学問への興味を持ってもらわないといけないのに、相手に伝える技術を持っていない。教える技術を養ってほしい」
まず経営から
――そのためには、まず何が必要でしょうか。
「大学の経営から変えないと始まらない。ちゃんとした経営者がやるべきだ。大学といえども(資金や人材などの)インプットに見合う成果であるアウトプットを求める仕組みが必要だ。経済合理性を基準にすべきだが、大学には企業に義務付けられているレベルの会計基準が導入されていない。そんな状況でどう運営できているのか不思議なくらいだ。大学運営が立ち行かなくなるまで分かろうとしないのか。企業のような会計基準を導入すれば、現実が見えるはずだ」
「社会が複雑化、多様化する中で、大学を文部科学省が監督しているのもおかしい。学問の自由が求められる大学を国が管理していいものなのか。自由な発想を生み出すためには、国の規制は不要なのではないか」
学生は知識不足
――そんな大学で学んだ学生をどう見ていますか。
「世の中で生きていくのに必要な基礎的な教養や知っておくべきことを知っていないし、知識の絶対量も少ない。そのために適切な判断ができない。もっと知識を詰め込まないと、自分が進んでいる道が世の中の方向性に合っているのか分からない。自分の判断が正しいかどうかを常に意識して行動することを習慣付けるべきだ。実業界は自分で考えて、自分で結論を出して実行できる人材を求めている」
――これからの大学は学生に何を教えればいいですか。
「社会に望まれるビジネスはどのようなものなのか、社会により貢献できる経営のあり方、人間のあり方を教えてもらいたい。会社員製造機関ではだめで、起業家の育成が大切だ。大学や大学院でそうした講座も出てきたが、小手先だ。経営マインドを持つ人材が大学から輩出されないから、そのための機関も自前で作った。世の中を変えるような仕事ができる人材を育てたい」
――ユニクロで大学1年生でも内々定を出す選考制度を始めたのは、大学教育に期待していないからですか。
「新卒一括採用を前提とした『倫理憲章』のような仕組みは主要国では存在しない。1年生でも、わが社で将来、どのような社会人になっていくのか目的意識を明確に持つ学生に内々定を出し、卒業後の入社を待つ。昨年は約10人を選んだ。大学1年生でも内々定を出すのは行き過ぎかもしれないが、それくらいでないと大学教育がこのままでいいのかというメッセージが伝わらないと思ったからだ」
---------------------------------
そして、「聞き手から」という後書きも秀逸でした。
こちらも、引用してみます。
---------------------------------
硬直した組織、現実直視せず
「おかしいです」「あり得ない」「よくないです」「最悪だよね」。柳井氏に質問をぶつけるたびにこうした言葉が繰り返された。それほど現在の大学の存在そのものが奇怪に映っているのだろう。「(大学自らは)つぶれるまで分からない」という発言は、大学改革ではなく、作り直しを求めているのだ。
なぜ、そこまで舌鋒(ぜっぽう)鋭くなるのか。それは米国、中国、欧州などに進出し、グローバルな競争社会に身を置き、教育や人材育成の重要性を痛感したからだ。そうした経験があるからこそ、柳井氏は自由な競争が社会を良くし、成長の果実を手にできるようになるための舞台装置だと確信している。
日本は資本主義、自由主義の国なのに、大学など教育機関には競争という舞台装置が組み込まれないことにいらだちを覚えずにはいられないのが心境だろう。企業経営では常識になっている競争を大学に持ち込むことが改革の第一歩と考えているようだ。
硬直した大学や大学院から輩出される人材も硬直し、それが日本社会全体を硬直させてしまうことを柳井氏は危惧する。内々定を1年生でも出すのは大学や学生にまずは意識を変えさせようとする仕掛けだ。
世界の中で存在感が低下する日本の問題に向き合おうとしない大学にいらだつ柳井氏。現実を直視しないのは「もはや大学以前の問題かも」という言葉には、大学が自らの力で変わることへの疑念も感じられた。
(編集委員 田中陽)
---------------------------------
さて、長々と引用しましたが、この現状の多くは、ほとんどが「文系の学部・学科」に当てはまるのではないかと思います。
ユニクロが採用するのは文系の学生が多いでしょうから・・・。
理系の学部・学科の学生は論文を英語で書いたり、日本国内の学会も英語での発表が当たり前になったりしていますので、文系の学生よりも「グローバルな経験」を沢山しているのではないでしょうか。
追記
大学教育を否定する、ユニクロ「大学1年4月採用」の衝撃 - ニューズウィーク日本語版
Posted by 百武塾 at 20:15│Comments(0)
│進路